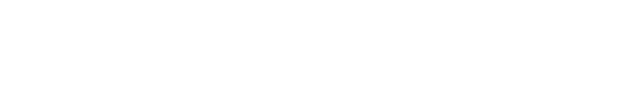白内障
1. 白内障とは
水晶体の濁りのことを「白内障」と呼びます。水晶体とは、カメラでレンズに当たる部分で、目に入ってきた光を屈折させ、網膜に像を結ぶ役割をしています。
白内障の原因としては、加齢によるものが多いですが、糖尿病、ステロイド、アトピー、外傷、紫外線など様々な要因で起こります。
白内障進行の本体は、クリスタリンと呼ばれるタンパク質の変性です。
外部からの物理的な刺激、紫外線、また内部からの酸化的ストレス、熱などによってクリスタリン中のアミノ酸残基に化学的な修飾が生じると、クリスタリンに変化が起き、最終的に水晶体が混濁し、白内障が生じてしまいます。
2. 白内障の濁り方
白内障の濁り方を説明するのに、まず水晶体の構造を理解する必要があります。
水晶体は直径9mm、厚み4mm程度のお椀型の形をしており、さらに中央部に核という構造を認め、皮質という皮に包まれています。皮質は、玉ねぎのように何層にも重なった線維状の組織で構成されています。皮質の外側には、嚢という厚み数μmから20μm程度の薄い膜を認めます。これらの構造が濁ることによって、白内障は大きく3つの名称に分類されます。
- 皮質白内障
- 核白内障
- 後嚢下白内障
3. 白内障の症状
白内障の濁り方によって症状が異なりますが、一般的には以下のような症状がおこります。複数の症状が出る場合もありますが、どれか一つだけの症状が強くでる場合もあります。
- 視力低下
- かすみ(霧視)
- 膜がかって見える
- まぶしさ(羞明)
- ものが二重に見える(単眼複視)
- 暗く感じる
- 今まで使っていた眼鏡が合わなくなる
そもそも、水晶体が濁ることでなぜ上記のような症状がおこるのでしょうか?
それは、主に、1.散乱と2.収差という現象で説明されます。
- 散乱・・・光が様々な方向に拡散してしまう現象
- 収差・・・光が理想的な一点に集まらない現象
白内障になると、散乱および収差が増加してしまい、結果、コントラスト感度の低下、水晶体屈折率の変化、グレア障害が生じ視機能が低下してしまいます。
4. 治療に関して
白内障は、手術によって低下した視機能の回復が望める疾患ですが、症状が軽度の場合は無理に手術を行わず、点眼治療などで経過をみることがほとんどです。
点眼治療については、あくまで白内障の進行を抑えることが目的で、水晶体を透明に戻すことはできません。自覚症状が進行してしまった場合や白内障によって眼内の炎症が起きてしまった場合、隅角が狭くなり緑内障の悪化が危惧される場合などは、積極的に手術を勧めております。手術の詳細につきましては、白内障手術のページをご覧ください。
白内障の進行を抑える代表的な点眼薬